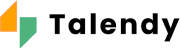2025-11-20
【イベントレポート】大手企業・スタートアップが描く「高度IT人材」獲得と組織変革の最前線 〜経済産業省IJTBプログラムが示す、グローバル競争を勝ち抜くための日印協業モデル〜

2025年11月13日、フォースタートアップスが主催するGRIC2025において、日本の大手企業とスタートアップが「インド高度IT人材との協業」というテーマで議論を行いました。世界的な技術競争が激しさを増す現在、日本企業が生存戦略としてなぜインドを選ぶのか、株式会社ログラスの伊藤博志氏、株式会社IHIの下村琢磨氏に、Tech Japanの西山がモデレーターとして伺いました。
本セッションでは、経済産業省「India Japan Talent Bridge(IJTB)」プログラムと連携し、2社のインドの高度IT人材を起点とした組織変革、企業文化の再設計、そしてイノベーション創出に向けた具体的な取り組みを明らかにしました。

モデレーター:西山 直隆 / Tech Japan株式会社 Founder CEO
インドのシリコンバレーと呼ばれるIT・テクノロジーの中心、ベンガルール在住。 デロイトトーマツグループにてベンチャー企業の成長支援に従事。当時、最年少部長に就任。その後、アジア地域統括としてインドチームを立ち上げ多くの日印ビジネス連携を創出。2019年、インドの力で日本企業の可能性を拓くことを目的にTech Japanを創業。インド最高峰の理系教育機関であるインド工科大学(通称IIT)と独自に提携し、学内で活用されている唯一のリクルーティング・プラットフォームを開発。現在、連携しているIIT卒業年度の学生のうち3人に1人が登録する、最大のIIT人材データベースを運営している。データを活用した開発組織の戦略策定、人材採用&開発チームの構築、人材が活躍できるための運用支援、インドにおけるグローバルケイパビリティセンター(GCC)の構築支援まで、一気通貫して日印テクノロジー分野の連携を推進する。
高度IT人材の獲得における課題とインドへの注目
西山:
ではここから、「高度IT人材の獲得と組織変革の最前線」というテーマで進めたいと思います。まずは伊藤さん、ログラスとして現在どんな課題意識を持って人材採用に取り組まれているかお伺いできますか。
伊藤:
ログラスは今シリーズBのスタートアップとして、創業6年目の会社です。
プロダクト開発を進める上で、かなり高い基準でエンジニアを採用しています。ただ日本国内だと、基準を満たす方の応募がそもそも少なくて、来ても選考を通らない。ここがまず大きな壁になっています。
3年前に私が入社した時はエンジニアが15名でしたが、今は70名くらいにまで増えています。このスピード感で採用を続ける必要がある中で、日本だけで人材を確保するのはもう難しいと強く感じています。
西山:
スタートアップとして知名度もあり、70億円規模の投資も受けているログラスさんでも「エンジニアが足りない」のが現状なんですね。
伊藤:
全然足りないです。外から見たブランド力ほど、採用マーケットでの供給量が追いついていない。優秀なエンジニアは国内ではかなりの流動性の低さで固まってしまっていて、特に即戦力経験者は取り合い状態です。だからこそ、アジアに目を向ける必要があると考えました。

ゴールドマン・サックスのテクノロジー部に新卒入社後、同社の基幹システム開発に従事。その後、VP/Senior Engineerとしてプラットフォーム開発に携わり、同社発のOSS戦略を牽引。スタートアップ2社を経て、READYFORに入社し、執行役員VPoEに就任。エンジニア組織のマネジメント、決済基盤の刷新や新規プロダクト開発を牽引。2022年10月に株式会社ログラスの開発部へエンジニアとして入社。EM、VPoEを経て2024年11月より執行役員CTOに就任。
西山:
その中でもインドに注目された理由は?
伊藤:
まず絶対数です。世界的に見ても、高度IT人材の「量と質」が両立している国はほぼインドしかない。時差が少ない、英語でコミュニケーションできる、文化的にもアジアで近い。ベトナムやインドネシアも検討しましたが、経験の深さと専門性ではインドが突出しています。そこで昨年からインドでGCC(グローバル・ケイパビリティ・センター)を立ち上げ、本格的に経験者を採用し始めています。
西山:
ありがとうございます。では続いて下村さん。100年以上続くIHIのような大規模な製造業だと、IT人材のイメージが湧きにくいという声もあります。その点も含め、なぜ今インドなのか教えてください。
下村:
製造業の世界は長らく「メカの人材」を中心に採用してきました。しかし今は事業戦略を進める上で、「メカ+IT・電機」の知見が必須になっている。例えばハイブリッド化など、取り組むべきテーマが山ほどあるのに、国内で採用できるのはメカ中心の人ばかりで、電機の基礎を理解していない。そんな人材が大半なんです。
西山:
国内で必要な人材が採れないと。
下村:
優秀なIT人材はWebサービスやテック企業に行く。製造業を志望する人は減っていて、社内にIT人材のパイプラインが足りない。戦略を実現するために必要なのに、どう逆算しても国内だけでは足りないんです。「どこなら採れるのか?」と考えた時に、自然とインドに行き着きました。

IHIは1853年の造船業を皮切りに始まり、近年は大規模プラント・インフラから量産機種まで幅広い製品群を持つコングロマリットとして事業展開。IHIアカデミーは活動開始3年目となった今春、アカデミー長に宇宙飛行士の野口聡一を迎えた。今後のグループ経営を想定し、その舵取りを担っていく人財に求める人物像の整備や、候補となる人財の発掘・育成・配置を一気通貫で手掛けるために、役員や社員との対話を重ねている。
西山:
お二人とも「国内人材だけでは戦略が成立しない」という点では全く同じですが、その解決策は企業の状況によって大きく違う。
日本の大企業、そして急成長スタートアップ。その両方が「国内人材だけでは戦略が成立しない」という同じ壁にぶつかり、インドという選択肢を取っています。まさに「組織の戦略にフィットしたインド活用」を体現されていると感じます。
インド人材採用の具体的な取り組みと成果
西山:
日本企業によるインドの新卒採用について、下村さんに伺います。IIT(インド工科大)の学生向けインターンシップを導入されていますが、実施内容や現場の反応を教えてください。
下村:
Tech Japanのネットワークを活用し、IIT23校に向けてインターンを募集しました。IITは「インド版MIT」とも言われ、GoogleのCEOなど世界的企業のリーダーを多数輩出しています。彼らは学生の段階から年収2,000〜3,000万円クラスの企業へ内定を狙い、アメリカや欧州へ挑戦しています。
日本の製造業がその給与帯の経験者を中途で採用するのは現実的ではありません。そこで「学生時代に日本でキャリアを積むことで希少なプロフェッショナル人材になれる」という価値を示し、新卒段階から関係構築するモデルを選びました。
ただ、日本企業の知名度が低いため、当初は「IHIってどこですか?」と鼻で笑われることもありました。そこで、まずはインターンの場を提供するところから始めました。
西山:
インターンでは、具体的にどんな業務を行ってもらったのでしょうか?
下村:
IITの学生の優秀さは聞いていましたし、私自身が選考に携わるうえで、この方は何をしたくてインターンに来ていただいたのかもわかっていました。そこで、単純作業ではなく私自身の戦略立案を学生に手伝ってもらう形を取りました。私が考えている論点を共有し、「あなたならどう考える?」と問い続ける高度な課題設定でした。
日本の理解の土台が必要なので、大学の授業などにも同行してもらいました。「こんなインターンは見たことがない」と、学生にも協力いただいた方にも驚かれましたし、社内からも当初は「戦略情報を学生に見せるのか」と抵抗がありましたが、「新しい世代と協働しないと変われない」と説得して進めました。
西山:
初年度の応募は?
下村:
300名超です。その中から3名がインターンに参加し、3名全員にオファーを出し、全員が承諾しました。
西山:
IT人材の新卒採用が難しいとされる日本企業が、トップ層の学生から100%の受諾率でオファーを受諾されたのは非常に象徴的ですね。今年は応募数が1,000名を超えたと聞き、インドのスケーラビリティを感じました。
続いて伊藤さん。経験者採用を軸にインドでGCCを立ち上げていますが、取り組みを教えてください。
伊藤:
当社は資金調達を経てマルチプロダクト化を進めており、即戦力が不可欠でした。社内には英語で開発できる人材が少ないため、インドに完全に独立した開発組織を作りました。ただしオフショアの外注の組織として切り離すのではなく、国内チームと同じ採用基準・品質基準を適用しています。
Tech Japanに支援いただき、約60名の応募から2名を採用しました。非常に優秀で、起業経験者も多い層でした。
日本のプロダクトマネージャーが要件を考えた上で、グローバルプロダクトマネージャーと連携し、スクラムを回しながら国内要件に合った機能開発を進めています。その過程ではユーザーの声を直接取りに行き、コミュニケーションを取りながら開発を進めています。

組織変革と人材活用における課題
西山:
ではここからは、実際に運用してみて感じた「難しさ」の部分を伺えればと思います。0→1の立ち上げ期は成果も見え始めてきた一方で、いろいろ大変なこともあったはずですよね。半年、1年と振り返って「ここがきつかった」という点をぜひ共有いただけると、皆さんの理解が深まると思います。伊藤さん、お願いします。
伊藤:
まず、新規事業のプロダクト開発にあたっては日本側がしっかりワークフローを整備してくれていたので、インド側はそこに接続するかたちで開発していきました。
ところが、独自開発の部分がとても優秀な一方で、既存プロダクトの品質基準と噛み合わない場面も出てきて。アジャイル開発なので当然、小さな失敗を次で改善するという流れなんですが、これが物理的に離れているだけで、あたかも「悪いことが起きたような感じ」が増幅されるんです。
西山:
距離があると、国内で一緒にやっているときの「失敗も含めて一連の流れが見える感じ」が薄れますよね。
伊藤:
国内だと失敗も次の改善も全部見えるのに、物理的に離れていることで「失敗だけが伝わる」ことがある。言語も文化も違うからコミュニケーション頻度が落ちた瞬間、不安や疑念が膨らんでしまう。心理的にも、うっすら不安感を抱いていると「やっぱり良くないことが起きた」と失敗に目が向いてしまうんですよね。
西山:
そのギャップを埋めるために、具体的にはどんな取り組みを?
伊藤:
カルチャーのインストールを徹底しています。ログラスはミッションやバリューをとても重視する会社ですが、それを同じ強度でインド拠点にも入れていかないと共有基盤が揃わない。
なので、ジョイン直後は日本に来てもらってベースラインを揃えてもらっています。また些細なことでも、インド側から日本への発信を意識的にやっていかねばと改めて思っています。
西山:
伊藤さん自身も1〜2ヶ月に1度と、頻繁にインドと日本を往来してコミットされていますよね。日本側メンバーをインドに連れていったり、逆に現場エンジニアを日本に呼んだり。
伊藤:
Tech Japanさんに紹介してもらって色々なGCCを視察したときにも、現地のリードがとにかく「信頼性がすべてだ」と繰り返していて。やっぱり「拠点に誰かがいる」ことだけでもカルチャーギャップを埋めるんだなと実感しました。
西山:
オフショアとは違う、まさに地道な「仲間」としての関わり方ですね。外注だったら成果物だけ見ればいいけど、インハウスなら価値観やプロセスまで共有しないといけない。
西山:
下村さんのほうでは、現場では相当なインパクトがあったのではないでしょうか。楽天で大きな変革を進めてこられた方が、伝統あるIHIに来て「イノベーションだ」と人材を連れてくる。混乱や抵抗があったのではと思います。そのあたり、どのように向き合われたのか伺いたいです。
下村:
「やっぱり来たか」という反応はありました。私が楽天出身ということで、社内ではいつか何か仕掛けると思われていたんでしょうね。そこにインド人材を連れて来たものですから、「ほら始まった」と。ただ、最初に来るIIT出身の若者たちには何の悪気もありません。だからこそ、期待と現実とのギャップを生まないよう、丁寧にコミュニケーションを重ねることを最優先にしました。
彼らは本来、GAFAMやコンサルなどの選択肢を持っていた人材です。それを捨ててIHIを選んでくれた。その背景には、家族や友人から「なぜIHIなのか」という声が必ずあります。だからこそ、IHIという職場が彼らにとって将来に希望を感じられる場所でなければいけない。困ったことや気づいたことは遠慮なく言ってほしいと、繰り返し伝えています。
最初につまずけば、「もうインド人材を日本で雇うな」という話になりかねませんから、踏み出すなら最初が何より肝心だと痛感しています。

西山:
コミュニケーションに関して、具体的にはどのような取り組みを進めているのでしょうか。
下村:
まず「二重のメンター制度」を作りました。業務上の上長とは別に、日本での生活・文化・ビジネスマナーについて何でも説明できる解説役を置く仕組みです。教育背景も文化も違うので、前提が分からずつまずくことが多い。その「なぜそうなるか」を丁寧に説明する役割です。
さらに、採用責任者である私自身が、彼らとまめに「今日はどうだった?」などホットラインでやり取りしています。日本では「なぜかは分からないけれどルールだから」という状況が多いですが、外国人の方にはそれが理解されにくい。萎縮せずに活躍していただけるように努めています。
西山:
単に採用して終わりではなく、「寄り添い続ける覚悟」が必要なんですね。
日印50万人交流へ。IJTBプログラムが描く新たなステージ
西山:
本日お二人の話を伺い、改めて共通して感じたのは、インドの高度人材には「質・量(スケーラビリティ)ともに大きな可能性がある」という点です。一方で、受け入れる組織の体制づくりには依然として課題も残っています。しかしその課題は、日本側が能力を引き上げる機会にもなる。そう強く感じました。
さて最後に、このセッションについて背景をご説明します。
本日は、経済産業省が推進する India Japan Talent Bridge Program(IJTB) のスポンサーセッションとして実施しています。当初、日本とインドの政府間では「5年間で5万人の人材交流」が掲げられていました。ところが約3か月前、モディ首相の来日を機に、この枠組みは大きく引き上げられ「5年間で50万人」という、さらに大規模な交流を目指す発表が行われました。
我々がプログラムとして具体的に取り組んでいることを説明します。
まず、IIT(インド工科大学)の教授陣を日本へ招聘するプログラムです。1週間、日本企業を訪問し、日本の技術や現場を直接見ていただきます。IHI様、ログラス様にも受け入れのご協力をいただきました。教授の皆様には、日本で活躍するIIT卒業生の姿や、日本の技術的な強みを深く理解いただく機会になっています。

同時に、日本企業をインドのIITへ派遣する取り組みも行っています。現地で学生向けの講演や質疑応答を行い、学生との接点を増やしていただく内容です。講堂には多い時で3,000名ほどが集まるほどで、反響の大きい取り組みになっています。日本という国や技術について、十分に知られてこなかった現実を踏まえると、重要な意味を持つ活動です。

今後は、この交流を踏まえたインターンシップの受け入れをさらに拡大していきます。日本での受け入れ、オンラインでの実施、あるいはインド側拠点での受け入れなど、形式も柔軟に設計しています。こうした取り組みには、経産省からの資金的な支援も含まれます。
また、取り組みの成果を広く共有するため、12月と1月に成果報告会の開催を予定しています。日本企業がインドの優秀な学生とつながる機会を、より広く提供していきたいと考えています。関心をお持ちの場合は、Tech Japanにぜひお声がけください。
西山:
最後になりますが、お二人から一言ずつお願いします。
伊藤:
本日はありがとうございました。私たちログラスも、インド人材と共に働く中で、まだ多くを学び続けている段階です。今日お話しした内容も含め、今後さらに取り組みを深めていきたいと考えています。本日はありがとうございました。
下村:
外国人を「安価だから採用する」という発想は、もはや現実にそぐいません。高い対価を払ってでも採用すべき人材である、という認識が組織に根付かなければ、グローバル人材活用は進まないと考えます。本日の議論が、考えるきっかけになれば幸いです。ありがとうございました。

インド高度IT人材の採用・組織構築・GCC(グローバル・ケイパビリティ・センター)運営についてのご相談は、Tech Japanへお気軽にお問い合わせください。
お問い合わせは【こちら】から