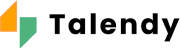2025-08-26
【2026年最新】グローバル・ケイパビリティ・センター(GCC)とは?日本企業のインドGCC活用事例とスタートアップ向け導入ガイド
グローバル・ケイパビリティ・センター(GCC / Global Capability Center)とは?
グローバル・ケイパビリティ・センター(GCC)とは、グローバル企業がIT・オペレーション・研究開発などの機能を集約・展開する拠点として、特にインドなど技術力に優れた国に設立する拠点です。

オフショア開発やBPOとGCCの違いは?
GCCは、オフショア開発や従来のBPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)とは異なり、単なる業務の単純な切り出しや外部委託ではなく「自社による戦略的内製化」を特徴とします。
最先端技術の研究開発など、経営上の重要度が高い機能を担い、知的資産やプロセスノウハウを継続的に蓄積・活用することが可能で、企業の中核的な価値創造を担う役割も果たします。

「海外拠点」はコストセンターから価値創造の中核へ
企業が海外拠点を設ける目的と形態が時代とともに変化し、海外拠点のあり方は進化してきました。大きく分けて、以下の3つのフェーズで捉えることができます。

- フェーズ1:BPO(Business Process Outsourcing)時代
1990年代後半〜2000年代、インターネットの普及や通信技術の進歩により、遠隔地との連携が容易になったことで盛んになったのがBPOです。
経理・人事・カスタマーサポートなどの定型業務を低コストで業務を回すことが主眼で、本社が細かく指示を出す「指示命令型」が基本でした。 - フェーズ2:GIC(Global In-house Center)時代
BPOによりコスト削減は実現できたものの、品質管理やセキュリティ、知的財産保護、企業文化との整合性などに課題が生じることがありました。これらの課題を受け、グローバル企業による自社運営の海外拠点の設立がみられるようになりました。GCCの前身ともいえる「GIC(グローバル・インハウス・センター)」です。
IT開発やR&Dなどの高度な業務にも取り組むようになり、「内製化されたオフショア」としての色が強まりました。まだ本社の指示に従う傾向が強いものの、BPOよりも自律性が高まります。 - フェーズ3:GCC(Global Capability Center)時代
2010年代後半からはデジタル化の加速によって高度IT人材の需要が世界的に高まり、本社のある国だけでは十分な人材を確保することが困難になりました。
そこで、海外拠点を単なるコスト削減や効率化だけでなく、イノベーションのハブとして活用し、企業の成長戦略に直接貢献させたいというニーズが高まりました。
GCCは今や本社の指示を受けるだけでなく、自律的にイノベーションや価値創出を担う「共創型」モデルへ進化。AIやデジタル技術の発展、優秀人材の争奪戦の中で、企業の競争力の中核を担う存在となっています。
生成AI登場後、高度IT人材採用は「量」より「質」へシフト

この変化は、開発リソースの「量」のみならず「質」を重視する方向への大きな転換を意味します。
GCCはコスト削減を超えた「価値創出拠点」へと進化しており、生成AI時代の開発体制再構築における中核戦略として注目されているのです。
なぜ今GCCが注目されるのか(グローバルと日本の視点から)
世界1,800社以上のグローバル企業のGCCを支えるインドの成長力

前述のとおり、世界のGCCの50%以上がインドに集中しています。インド内のGCCの数は2024年時点で1,800社に達し、130万人の雇用につながっています(JLL、2024年2月)。
毎年115社のGCCがインドにおいて新たに誕生し、2025年までに1,900社、2030年までに3,000社を超えると予測されています。

インドにとっての成長基盤は、生産年齢人口の豊富さと若さです。
2025年時点の人口は約14.6億人に達し、既に中国(約14.1億人)を上回り世界最大人口の国となりました。人口の半数近くが35歳未満で、中央値は約29.5歳に過ぎません。
インドのGDPは主要経済国の中で最も高い成長率を誇り、IMFによれば2024〜2025年度における成長率は6.5%と予測されています。
中でも情報技術(IT)・BPO産業はインドGDPの約7〜7.5%を占め、2023年には約540万人が従事する巨大産業です。IT・ソフトウェア輸出額は2,540億ドルにものぼります。

このうち、主要都市であるバンガロール(ベンガルール)には100万人に達するIT従事者が集積し、「インドのシリコンバレー」として世界中のSaaS企業やテック企業の拠点が集中しています。
また、インド工科大学(IIT)やインド理科大学院(IISc)などから毎年大量の優秀な人材が輩出されており、人材の量と質の両面で世界トップクラス。この知的資源が、グローバル企業にとっての戦略的拠点選定を後押ししているのです。
欧米企業のGCC活用状況(事業戦略・イノベーションハブ)
欧米のグローバル企業は、GCCを単なるオフショアの業務委託拠点としてではなく、自社の戦略を牽引する「イノベーション・ハブ」としてすでに積極的に活用しています。

特にベンガルールには、Google、Microsoft、Amazon、Intel、IBM、Yahoo!、SAP、Oracle、Facebook、SamsungなどのIT企業や、GE、Philips、Airbus、Bosch、トヨタ、ソニー、ホンダなどのGCCが存在。コア機能の一部を現地に移し、戦略的な拠点として重要な役割を果たしています。
ベンガルールでは最大6,000万円超の投資助成も。2024年にはGCC設立を後押しする政策も登場
現地政府の支援政策もGCC活用の追い風となっています。2024年11月には、バンガロールが位置するインド南部のカルナータカ州政府が、インドで初めてGCCに特化した政策を発表しました。
この政策では人材育成の補助や設備投資の助成、認証や特許出願に関する優遇が受けられます。
カルナータカ州政府はこの政策により、2029年までに新規で500拠点のGCC誘致、35万人の新規雇用の創出、500億ドルの経済効果創出を目指すとしています。
企業が採用した学位取得者に対し、1人当たり3万6,000ルピー(約6万4,800円、1ルピー=約1.8円)、ディプロマ(卒業認定)取得者は同1万8,000ルピーまでの育成費用の20%を還付。
インターンシップにかかる費用のうち半額を還付(最大3カ月間、1人当たり月額5,000ルピーが上限)。
(2)現地エコシステム整備
ベンガルール市内部での設備投資助成(最大2案件、総額の40%、4,000万ルピーが上限)。
(3)ベンガルール以外の地域に対するインフラ整備と投資優遇
新規GCCに対するオフィス賃料を一部還付。
(4)規制緩和
ベンガルール市内部に所在のGCCに対して、品質認証取得手数料の半額を還付(上限60万ルピー)。
ベンガルール市内部に所在のGCCに対して、国内特許出願時の法定手数料の半額を還付(上限20万ルピー)。
戦略コンサルタント、不動産サービス、法務・税務の専門家などのサポートが受けられる、GCC専用の相談窓口を設置。
インド初のグローバル・ケイパビリティー・センター政策、カルナータカ州が発表(インド) | ビジネス短信 ―ジェトロの海外ニュース
日本のIT企業のGCC活用例
日本ではIT人材の不足が深刻化しており、2030年には最大で79万人のIT人材が不足する可能性があると予測されています(経済産業省)。
スピード感を持って価値あるサービスを提供するためには、国籍や地域にとらわれない多様な人材の登用が不可欠です。グローバルな人材の活用や多様性を前提としたチームづくり、世界基準の採用体制を整えることが、日本企業にとって競争力強化の鍵となります。
欧米企業に比べ、日本企業のGCC進出はまだ始まったばかりといえる段階ですが、国内での高度IT人材の不足や海外市場への対応力強化を見据えて、インドにおけるGCC設立を模索・実行する企業も増えつつあります。
特にメルカリ、楽天、マネーフォワード、ログラスといったIT企業を中心に、インドの高度人材を活用した開発拠点の設立が進んでいます。以下に具体例を見てみましょう。
マネーフォワード:国外3拠点目として「SaaSキャピタル」にGCC設立
FinTech領域でサービスを展開するマネーフォワードは、2025年2月にインド・チェンナイに新たな開発拠点・マネーフォワードインディアを立ち上げました。
拠点を構えるチェンナイは、インド国内でもITエンジニアの育成に力を入れており、世界的なSaaS企業の開発拠点が集まる「SaaSキャピタル」として注目を集める地域です。
マネーフォワードはこれまでもベトナム・ホーチミンおよびハノイに開発拠点を設けており、チェンナイは3拠点目の海外展開です。時事通信によればこれらの拠点と日本国内のチームが連携し、主力プロダクトであるバックオフィス向けSaaS「マネーフォワード クラウド」の開発を進めていく予定としています。
【出所】
マネーフォワードグループ、インド国内初となる開発拠点をチェンナイ市に開設 – 株式会社マネーフォワード プレスリリース(2025年1月28日)
インド初の開発拠点公開 マネーフォワード、高度人材獲得へ
ログラス:2025年、ベンガルールで開発拠点の構築を始動
クラウド経営管理システムを提供するログラスは、2024年7月のシリーズB・70億円の資金調達を期に、プロダクト拡充・新規事業開発の体制の強化を進めています。
その中核を担う戦略が、海外開発拠点の立ち上げによる開発のケイパビリティ向上です。
ログラスが拠点立ち上げに際してパートナーとして選んだのは、Tech JapanのGCC構築支援サービス「Talendy GCC」です。同社は今後、インドをはじめとした海外開発拠点を軸に、世界に通用するプロダクトの開発を強化していくとしています。
【出所】
ログラス、Tech Japanと共同でインド開発拠点(インドGCC※1)の構築を本格始動し、グローバル開発体制を強化 – 株式会社ログラス プレスリリース(2025年5月9日)
GCCはスピードと柔軟性を求めるスタートアップに最適な選択肢
急成長を目指すスタートアップにとって、プロダクトの開発スピードと市場投入までのスピードは生命線です。
特に内製志向が強く、自社で技術力を確保しながらプロダクトを磨き込んでいきたい企業にとって、GCCは非常に有効な選択肢です。

GCCに向いている企業
テクノロジーと人材に対して積極的に投資し、開発スピードを加速させたい企業にとっては最適な選択肢です。特に、プロダクト志向で内製化を重視し、事業成長に必要なエンジニアリング体制を柔軟かつ主体的に構築したいスタートアップにフィットします。
GCCに向きにくい企業の特徴
一方で、GCCという形がフィットしづらい企業も存在します。以下のようなケースでは、BPOやオフショアの開発委託などの方が適している場合があります。
- 外注志向が強い場合
開発業務を外部パートナーに委託するスタイルを基本とし、内製チームを持つ意志が乏しい場合、GCCの自律性や長期的な運用メリットを活かしにくい場合があります。 - コスト削減を主目的としている場合
GCCは、単なる「コストセンター」ではありません。高品質なエンジニア人材の確保・育成に注力するモデルであり、単純な人件費圧縮を目的とする場合には、期待とのギャップが生じることがあります。 - 開発側が受託的に動く体制
本社主導で意思決定を一元的に行い、開発側が実装中心で動くような体制では、GCCの自走性を高めることが難しいケースもあります。特に現地で採用される優秀な人材ほど、自律的な環境や成長機会を重視する傾向があるため、モチベーション維持の観点で工夫が求められます。
初めてのインドGCC設立はパートナーを活用した導入がおすすめ
日本企業にとって「自前の海外拠点」はなぜ難しいのか
日本企業が、インドなど海外で初めて自社のGCCを立ち上げる際には、多くの障壁が待ち受けています。たとえば、次のような課題がよく見られます。

- 欧米流を前提としたマネジメント体制への不慣れさ
現地の優秀人材はグローバルな就労経験が豊富で、自律性の高い欧米式の評価・報酬体系やマネジメントスタイルに慣れています。評価や目標設定に独特のスタイルをもつ日本企業のやり方をそのまま適用すると、現地マネージャーとの間で認識の齟齬を生みやすい構造があります。 - 日本本社との意思決定プロセスのズレやタイムラグ
海外拠点が十分な権限を持てないケースが多く、日本本社に都度確認を求める構造では、迅速な意思決定が求められるグローバルな人材市場では出遅れてしまうリスクがあります。 - 「日本流の働き方」へのこだわりがカルチャーギャップを生む
細かな承認プロセスやマイクロマネジメントなど、日本的な働き方をそのまま持ち込むと、現地スタッフとの信頼関係構築に支障が出る場合があります。これにより、エンゲージメントや定着率が大きく下がってしまうケースも少なくありません。
加えて、日本企業の多くはグローバル人材市場における「雇用ブランド」が確立されておらず、GoogleやMeta、Accenture、TCSなどといった名だたるグローバル企業に比べて、優秀な人材にとって魅力的な就職先として認識されにくいという課題もあります。
特にインドでは、企業の技術的チャレンジ度やキャリアの将来性が強く意識されるため、企業のビジョンやプロダクトの魅力をどう伝えるかも重要です。
このような課題をクリアし、リスクを最小限に抑えながら、インドの高度IT人材の力を柔軟に活用する手段として有効なのが、信頼できるパートナーを活用した「段階的なGCC立ち上げ」です。
GCC設立パートナーの選び方:自社に合った支援を受けるために
GCC設立を成功させるには、自社の規模・目的・文化に適したパートナーを選ぶことが極めて重要です。プレイヤーごとに強みや支援スタイルは大きく異なります。

グローバル支援大手(ANSRなど)
【特徴】
ANSRをはじめとするグローバル支援大手は、すでに数百社以上の大規模GCC設立を手がけた実績を持ち、オフィス設立、採用、運営までを包括的に支援します。特に100人以上の体制構築や長期的な拡張計画に強みがあります。
一方、支援は基本的に英語で行われ、日本企業特有の文化や意思決定プロセスに対する配慮は限定的であるため、日本語対応や現地とのブリッジ機能は期待しにくいといえます。
【向いている企業】
- 大手企業やメガベンチャー
- 初期から数百人規模のGCCを想定している企業
- インドを戦略拠点として大規模に展開したい企業
- 英語でのコミュニケーションやグローバル基準のプロセスに慣れている企業
グローバル系コンサルティングファーム
【特徴】
マッキンゼーやデロイト、KPMGなどのコンサルティングファームは、戦略立案から法務・税務、IT基盤整備まで幅広い支援が可能です。多くは大規模プロジェクトやDX案件全体の一環としての支援が中心となり、将来的にはGCCを数十人〜数百人規模に拡張する意向がある大企業に適しています。
ただし、アプローチは比較的テンプレート化されており、意思決定や実行には一定の時間とコストを要します。
【向いている企業】
- 組織全体の再編や複数国への展開も同時に検討している大企業
- グローバルなコーポレートガバナンスや法務体制を重視する企業
日本企業のインド進出支援に特化したTech Japan
【特徴】
Tech Japanは日本企業に特化したGCC立ち上げ支援を行っており、10人以下のスモールスタートから柔軟に対応可能です。日本側との文化や業務理解を持つブリッジ人材を活用し、現地との円滑な連携を支援します。特に初めてのインド進出において、不安を解消しながら前に進めるサポートが得られる点が強みです。
【向いている企業】
- インド展開が初めての日本企業
- スピード感を持ってまずは10〜30人規模で始めたい企業
- 現地文化やマネジメントの違いに不安がある企業
世界トップクラスのエンジニア組織構築をもっと柔軟にする「Talendy GCC」
ここまで見てきたように、インドにおけるGCCは、日本の企業にとって極めて有力な開発戦略の選択肢です。一方で、自社単独での立ち上げには高いハードルがあるのも事実。言語、文化、意思決定プロセス、現地法務などは、いずれも無視できない課題です。
そこで「スモールスタートでインド開発拠点を経営戦略に組み入れたい」という企業に向けて、Talendy は、これまでにない柔軟なGCC導入の選択肢を提供しています。
特徴①:小規模から立ち上げ可能(Tech Japan Centerモデル)

Talendyでは、BOTモデル(Build-Operate-Transfer)を採用し、初期費用・リスクを最小限に抑えながらインド開発体制を構築できます。従来のように数百人単位の投資が前提となるのではなく、数名のコアチームからスピーディに立ち上げ可能です。
まずは少人数・試験的に開発をスタートし、成果やカルチャーフィットを確認した上で、必要であればそのまま内製化(自社拠点化)にも移行可能。成果が期待に届かなければ途中で見直すこともできる、柔軟な選択肢を提供します。
特徴②:日本企業によるインド開発の支援に特化した採用エキスパートが伴走
Talendyは、日本企業によるインド開発の支援に特化したチームです。
これまで150社以上の日本企業を支えてきた実績があるTalendyは、経験豊富な日本人コンサルタントがオンボーディングから日常の運用までを日本語でサポートし、日本的な業務文化や組織構造を理解したうえで最適なアドバイスを提供します。
海外人材採用に不慣れな企業でも、Talendyの採用エキスパートがインド人材とのマッチングからエンゲージメントまでを一貫して支援します。
2018年より経済産業省や在日本インド大使館とコンソーシアムを共同運営するなど、公的機関とも連携した信頼ある支援体制を構築しています。
特徴③:質にこだわった高度IT人材ネットワーク
Talendyはインド工科大学が導入している唯一のインターン・採用プラットフォームを提供しており、質の高い人材が在籍しています。
トップ1%のエンジニア層を中心に、1万人以上の人材データベースを保有し、高度な技術力と将来性を持った人材へのアクセスを可能にしています。
私たちTalendy自身のチームも多くのインドトップ人材を採用し、インド人エンジニアが多数在籍(全体の1/3)しています。自社での採用・エンゲージメント・マネジメントノウハウをクライアントにも惜しみなく提供いたします。
特徴④:オフィス・法務・会計・雇用管理まで包括支援
インドに現地法人がない企業でも、TalendyのEOR(雇用代行)サービスを通じて、現地の優秀なエンジニアを即座に採用・雇用することが可能です。
人材の雇用契約・給与・福利厚生・税務処理などの煩雑な業務はすべてTalendyが代行。法人設立にかかるコストや時間をかけずに、即戦力となるインド人材をチームに迎えることができます。
また、将来的な現地法人設立を見据えて、人材をプールしておくことも可能です。拠点設立のタイミングには、既に信頼できるチームが整っており、スムーズかつ効率的な内製化が実現します。
次の一歩を、インドの優秀な人材とともに
GCCの導入は決して「大企業だけの戦略」ではありません。今後の成長を加速させたいスタートアップや中堅企業こそ、柔軟で現実的なアプローチでの導入がカギとなります。
Talendy GCCは、そんな企業のための実践的なソリューションです。ご関心がある方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。